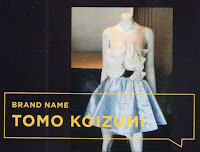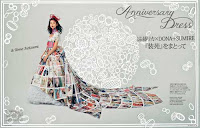「glee/グリー」「アメリカン・ホラー・ストーリー」などのプロデューサーとして知られるライアン・マーフィーが手掛けたテレビシリーズ「フュード/確執 ベティ vs ジョーン/Feud : Bette and Joan」は、ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードが初共演した「何がジェーンに起ったか?」の映画製作の舞台裏を描くということで、ジョーン・クロフォードの大ファン(勿論ベティ・デイヴィスも大好き)のボクとしては、何が何でも見逃すことができないと非常に楽しみにしていたのであります。(けいたいおかし参照)
しかし・・・日本では”スターチャンネル”(ボクは契約してない)での独占放映(2017年9月29日~)。それならば、アメリカ本国でDVD/Blu-ray化されるか、Netflixなどの配信を待とうと思っていたところ・・・本作に登場するオリビア・デハヴィランドご本人(101歳でご存命)が「無断で作品に使用された!」とクレームを入れて裁判沙汰に・・・その後に訴えは却下されたものの、DVD/Blu-ray化はお蔵入りのまま。ただ最近、ジョーン・クロフォードのファンサイトでエミー賞投票者向け(Fot Your Consideration=FYCという非売品)DVDセットが、アメリカのオークションサイト”eBay”で出品されていることを知って、先日(結構な高額で!)無事に落札!遂に「フュード/確執 ベティ vs ジョーン」を観ることができたのです。
伝説的に語り継がれるベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの確執は、二人が生まれたときから始まっていたと言っても良いのかもしれません。生まれてすぐ実の父親に捨てられた上に義父に手篭めにされたジョーン・クロフォードは、フラッパーダンサーからハリウッド女優に成り上がった”叩き上げ”女優。共演した男優は勿論、映画監督、照明や撮影のスタッフとも肉体関係を結んで、キャリアを築き上げていったと言われています。1930年代には美貌の”スター女優”として上り詰めるのです。
一方、父親とは不仲だったベティ・デイヴィスは、若くしてブロードウェイで頭角を現してハリウッドの招かれた”演技派”女優であります。歌になるほど(キム・カーンズの「ベディ・デヴィスの瞳)特徴的な瞳をもつベティ・デイヴィスは、一般的に”美人”というわけではありませんが、演技力は折り紙つき。外見を気にせず役柄になりきって、20代で二つのオスカーを受賞してハリウッドで最もリスペクトされる女優となります。
同時期に”ハリウッド女優”として活躍したベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの女優としてのスタンスは「水と油」で、常にお互いをライバル視する運命にあったのです。
一方、父親とは不仲だったベティ・デイヴィスは、若くしてブロードウェイで頭角を現してハリウッドの招かれた”演技派”女優であります。歌になるほど(キム・カーンズの「ベディ・デヴィスの瞳)特徴的な瞳をもつベティ・デイヴィスは、一般的に”美人”というわけではありませんが、演技力は折り紙つき。外見を気にせず役柄になりきって、20代で二つのオスカーを受賞してハリウッドで最もリスペクトされる女優となります。
同時期に”ハリウッド女優”として活躍したベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの女優としてのスタンスは「水と油」で、常にお互いをライバル視する運命にあったのです。
本作は、往年のハリウッド女優オリビア・デハヴィランド(キャサリン・ゼタ=ジョーンズ)とジョーン・ブロンデル(キャシー・ベイツ)が、ジョーン・クロフォードの死後の1978年にジョーン・クロフォードとベティ・デイヴィスについてインタビューで語る場面(1978年にイギリスBBC制作の番組『The Hollywood Greats』を元ネタにした架空のテレビドキュメンタリー)と、「何がジェーンに起ったか?」の舞台裏からその後を描く物語が、行き来しながら進行していきます。二人の女優としてのキャリアやゴシップ的な数々の逸話をインタビューという形で語らせることで、ジョーン・クロフォードとベティ・デイヴィスについて詳しく知らない視聴者にも時代背景が理解できるという構成となっているのです。
ペプシコーラ社長の夫と死別したジョーン・クロフォードが女優としての再起を狙って自ら企画を探すというところから本作の物語は始まり、ジョーン・クロフォードの死後に登場人物たちが彼女に思いを寄せる場面で終わることから・・・本作の「主役」はジェシカ・ラング演じる”ジョーン・クロフォード”であると思います。
ジェシカ・ラングは「アメリカン・ホラー・ストーリー」の常連キャストでもあり、”ジョーン・クロフォード”を演じるのに相応しい女優であることに間違いありません。ただ、生涯スレンダーな体型を維持して美貌を保ち続けたジョーン・クロフォードと比較してしまうと、ジェシカ・ラングの”恰幅の良さ”や”ナチュラルな老け具合”は目についてしまいます。
逆に、ベティ・デイヴィスを演じるスーザン・サランドンは本人よりスラっとした美人なので、二人の確執の要因のひとつであった「ジョーン・クロフォード=美貌のスター女優だけど演技の才能には欠ける」「ベティ・デイヴィス=個性的なルックスで美人ではないけど演技力は抜群」という二人の個性が薄れた印象は否めません。・・・とは言っても、ベティ・デイヴィスを違和感なく演じきったスーザン・サランドンもさすがです。
本作で再現されたシーンと実際の映像を比較している動画があるのですが、本物のベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの持つ「顔のパワー」には圧倒されます。
逆に、ベティ・デイヴィスを演じるスーザン・サランドンは本人よりスラっとした美人なので、二人の確執の要因のひとつであった「ジョーン・クロフォード=美貌のスター女優だけど演技の才能には欠ける」「ベティ・デイヴィス=個性的なルックスで美人ではないけど演技力は抜群」という二人の個性が薄れた印象は否めません。・・・とは言っても、ベティ・デイヴィスを違和感なく演じきったスーザン・サランドンもさすがです。
本作で再現されたシーンと実際の映像を比較している動画があるのですが、本物のベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの持つ「顔のパワー」には圧倒されます。
冒頭のインタビューシーンでオリビア・デ・ハヴィランドが語る「確執は決して”憎しみ”ではなく”痛み”なのです。/FUEDS are never about HATE. FUEDS are about PAIN」というのが本作の本質かもしれません。
同じ映画会社に所属しながら一度も共演することのなかったベティ・デイヴィスを担ぎ出したのは、誰あろうジョーン・クロフォード・・・露骨にライバル心を燃やしながらも歩み寄り、”若くない女優”を蔑ろにするハリウッド体質にタッグを組んで戦っていく様は、”フェミニズム”的なテーマでもあります。また、単に「確執のある女同士の戦い」という一層的な物語には終わらせてることはなく、映画会社の幹部などの一部の男性による支配から生み出されていた”不条理さ”は「#MeToo」運動に繋がっているようにも感じます。
ベティ・デイヴィスだけがアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたことで確執をさらに深めていく”くだり”や、「血だらけの惨劇」(めのおかし参照)などのサイコ・ビディ(Psycho-Biddy)と呼ばれる一連の熟女ホラー映画の再現は「おキャンプ」好きも満足させる作りとなっているのです。
ベティ・デイヴィスだけがアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたことで確執をさらに深めていく”くだり”や、「血だらけの惨劇」(めのおかし参照)などのサイコ・ビディ(Psycho-Biddy)と呼ばれる一連の熟女ホラー映画の再現は「おキャンプ」好きも満足させる作りとなっているのです。
本作では、ベティ・デイヴィスは従来のイメージどおり”強気”に(子供たちとの関係においての孤独感あるもの)描かれているのですが、対照的にジョーン・クロフォードには寄り添っているように感じます。二人が再び共演するはずだった「ふるえて眠れ」でのジョーン・クロフォード降板の顛末は、ジョーン・クロフォード側に同情的な視点で描かれますし、”プライドの高さ”に反しての”人間的な弱さ”もリスペクトを持って描かれているように思うのです。亡くなる直前、ジョーン・クロフォードの幻想の中で、ベティ・デイヴィスとの間に友情を結ぶのは”フィクション”ではありますが、それが”ジョーン・クロフォードの本望”であったような気がしてなりません。
ジョーン・クロフォードの死後、養女のクリスティーナ・クロフォード(本作には登場しない)が1978年に出版した暴露本「親愛なるマミー・ジョーン・クロフォードの虚像と実像/Mommie Dearest」と、それを原作にした1981年の映画「愛と憎しみの伝説/Mommie Dearest」(めのおかし参照)によって、ジョーン・クロフォードのスター女優としての輝かしい功績は「養子虐待女優」というレッテルを貼られて、とんでもないほど地に堕ちてしまったわけですが・・・本作で描かれるジョーン・クロフォードの姿によって、約40年ぶりに”その汚名”を少しでも払拭できたのではないでしょうか?
ジョーン・クロフォードの”いちファン”として涙が止まりません。
ジョーン・クロフォードの”いちファン”として涙が止まりません。
「フュード/確執 ベティ vs ジョーン」
原題/Feud : Bette and Joan
2017年/アメリカ
製作総指揮: ライアン・マーフィー他
演出 : ライアン・マーフィー
出演 : ジェシカ・ラング、スーザン・サランドン、ジュディ・デイヴィス、アルフレッド・モリナ、スタンリー・トゥッチ、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、キャシー・ベイツ
2017年9月29日よりスターチャンネルにて日本独占放映