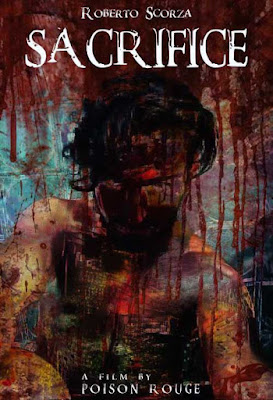「籠の中の乙女/Dogtoooth」(2009年)から注目してきた「ギリシャの新しい波」を代表するギリシャ人映画監督ヨルゴス・ランティモス・・・「ロブスター/Lobster」(2015年)以降は、活躍の場をイギリスに移して、英語による作品を制作しています。映画の中の言語が英語以外の場合、世界的な市場規模やメディアによる評価も制限されがちなので、賢明な方向性であることには間違いありません。
とは言っても・・・ヨルゴス・ランティモス監督とギリシャ人脚本家エフティミス・フィリップスとの共作による独特の世界観は「ロブスター」でも発揮されてしましたし、「聖なる鹿殺し キリング・オブ・セイクレッド・ディア/The Killing of Sacred Deer」(2017年)でもギリシャ悲劇をベースにしていたりと、「ギリシャの新しい波」らしいアイデンティティは踏襲されていたように思います。しかし、最新作「女王陛下のお気に入り/The Farvourite」は”雇われ”(?)監督という立場で制作された初のヨルゴス・ランティモス監督作品となるのです。
グレートブリテン王国の悪名高き(?)アン王女(オリビア・コールマン)の信頼を得ることは、政治的な主導権争いでもあります。王女の最も近い存在になっている女官長のレディ・サラ(レイチェル・ワイズ)は、対フランスの軍を率いる夫のモールバラ公と大蔵卿のゴルドフィンらと、さらに税金を国民に課してまでも戦争を続けたい推進派。
そこへ、サラの従姉で没落貴族のアビゲイル(エマ・ストーン)がレディ・サラを頼ってやってきます。召し使い同士のイジメに耐えながら、再び上流階級に返り咲きたいアビゲイルは、アン王女になんとかして近づこうとするのです。戦争反対派の野党のハーリーはアビゲイルを利用してアン王女とレディ・サラの動向を探ろうとしたり、アビゲイルに一目惚れしたマシャム大佐は何とかして手篭めにしようとしています。
英国宮廷の華麗ななるドロドロ・・・物語の焦点はアン王女、レディ・サラ、アビゲイルの3人で、舞台となるのもアン王女の宮殿内のみ。実際に政治や戦争の現場にいる男性たちはバックグラウンドで、女性たちがナチュラルメイクなのに、美しさにこだわっていた男性たちはカツラと化粧で滑稽な姿だったりします。レディ・サラの夫で戦争をしている当事者であるはずのモールバラ公は、影が薄過ぎて存在感が殆どないほどだったり。
数々の映画賞レースでも、オリビア・コールマン、レイチェル・ワイズ、エマ・ストーンの主演3人(賞レースでの扱いはオリビア・コールマンが主演でレイチェル・ワイズとエマ・ストーンは助演)が競っているのは、当然と言えば当然なのです。
自然光による撮影の宮廷絵巻というと「バリーリンドン」を思い起こさせますが、本作は全体的に画面は暗め・・・さらに魚眼レンズ並の広角での撮影を多用していて、宮殿で起こっている出来ごとを遠目で傍観しているかのような撮影方法です。これこそ、ヨルゴス・ランティモス監督らしいクールな視点だと思うのですが・・・めくるめく宮殿絵巻の美麗な映像を期待すると、少々地味な印象を与えるかもしれません。
ここからネタバレを含みます。
ある夜、レディ・サラの図書館に忍び込んだアビゲイルは、アン王女とレディ・サラがレズビアン関係であることを目撃します。アン王女に接近する機会を得たアビゲイルは、すかさずマッサージをする素振りから性的なサービス(映像では映しませんが舌でアソコを舐めた)をして、すっかりアン王女をそのサービスの”虜”にしてしまうのです。そして、アビゲイルは策略どおりアン王女直々の寝室つきの待女となります。
アビゲイルの次の目標はレディ・サラをアン王女から遠ざけること・・・レディ・サラの紅茶に毒を入れてしまうのです。森の中を馬で行く途中、毒が回ってレディ・サラは落馬してしまい、森のならず者の家に閉じ込められてしまいます。
レディ・サラが姿を隠しているのは、アビゲイルに肩入れしている自分を嫉妬させるためと邪推したアン王女は、捜索隊の派遣さえ出させず、アビゲイルはアン王女を取り込むことにまんまと成功するのです。上流階級への返り咲きを虎視眈々と狙っていたアビゲイルは、アン王女の計らいによりマシャム大佐と電撃結婚・・・自らの地位を確実にします。
森から大怪我をしてレディ・サラが宮殿に戻ってきますが、アン王女は野党の思惑どおり戦争終結を命令・・・戦争促進派のレディ・サラと夫のモールバラ公は追放されてしまうのです。宮殿に残されたのはアン王女とアビゲイル・・・自分の地位確保のためにアン王女を利用しただけのアビゲイルにはアン王女に対する情はありません。本当の意味で孤独になってしまったアン王女は以前に増してますます不幸になり、アビゲイルを徹底的に服従させる殺伐とした関係しかないのです。
エンディングでアビゲイルを従わせているアン王女の表情に、ウサギの群れ(アン王女は亡くなった17人の子供と同じ数のウサギを飼っていた)の映像がオーバーラップするのは、もはや自分に服従する者たちはウサギのようだ・・・というヨルゴス・ランティモス監督の皮肉のようにも思えます。正統派のドロドロ宮廷絵巻という題材により、脚本家エフティミス・フィリップスとの共作による不思議系映画というジャンルを超えて、監督としての資質を発揮したと言えるのかもしれません。
第91回アカデミー賞でも9部門最多10ノミネート(助演女優賞レイチェル・ワイズと衣装デザイン賞は獲れそう?)という評価を受けた本作・・・ヨルゴス・ランティモス監督は、もう「ギリシャの新しい波」というマイナーな存在ではなく、これからの「ヨーロッパ映画界の担い手」として認知されたといって良いのではないでしょうか?
「女王陛下のお気に入り」
原題/The Farvourite
2018年/アイルランド、アメリカ、イギリス
監督 : ヨルゴス・ランティモス
出演 : オリビア・コールマン、エマ・ストーン、レイチェル・ワイズ、ニコラ・ホルト、ジョー・アルウィン、マーク・ゲイティス
2019年2月15日より日本劇場公開