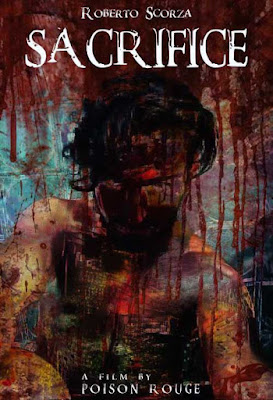サマセット・モームの短編小説「雨/Rain」(発表時は「サディ・トンプソン/Sadie Thompson」という題名)は、発表後すぐに舞台化され、演技派女優にとっては”演じてみたい役”のひとつかもしれません。「雨」を原作とした映画は、サイレント時代、トーキー初期、3D映画全盛期に3作つくられているのですが、それぞれ趣の違う作品となっているのです。
舞台となるのは、サモア諸島にあるアメリカ領のパゴパゴという島の村・・・そこに、サディ・トンプソンという派手な服装の娼婦らしき女性が、ホノルルからの船で到着します。同船していた宣教師のデヴィットソン夫妻やマックフェイル医師夫妻もサディと同じ島唯一のホテルに滞在することになるのですが、モラリストの夫妻らにとってサディの素行には目に余るものがあるのは当然です。
実はサディ・・・ある事件にサンフランシスコで巻き込まれて警察に追われている身で、逃亡先だったホノルルから逃げてきたところだったのであります。サディに一目惚れしてしまった駐留している海兵隊のオハラ軍曹は一緒にシドニーに移り住もうと誘うのですが、サディの素性を知ったデヴィットソン神父は自らの権限を使ってサディを強制的に本国へ送還させようとするのです。
見逃すように懇願するサディを宗教的な正論で跳ね返すデヴィットソン神父の言葉に、サディはキリスト教徒として開眼する(Born-Again Christian)に至ります。地味な化粧と服装で別人となったサディの信仰心から醸し出される美しさに、心を乱されたデヴィットソン神父は本国送還の前夜、サディの寝室に忍び込むのです。翌朝、漁師の網に引っかかったのは、自害したデヴィットソン神父の遺体・・・「男なんて汚らしいブタだよ」と捨て台詞を吐いて、サディは以前のような娼婦の姿に戻ります。
当然ながら、サディの寝室で何が起こったかは描かれません。ちょっとした謎なのですが、おそらくサディを強姦して自らの自責の念で自殺したということのようです。派手な娼婦がクリスチャンに転向して地味なったかと思ったら派手に戻るのも・・・神の教えを説いていた神父も実は他の男と同じように性欲をもっていたという”どんでん返し”(?)も通用しなくなってしまったのも、本作が前提としていた”モラル”自体が崩壊してしまった今では、どうでもいいような話かもしれません。
サディ・トンプソンを映画作品で最初に演じたのは、サイレント映画時代の1928年にグロリア・スワンソン(港の女/Sadie Thompson)で、原作の時代性と最も近いような気がします。とんでもない大女優だったグロリア・スワンソンは、姉御肌の高級情婦といった感じで・・・当時流行した”モダンガール”のような印象です。キリスト教に目覚めるシーンでは、サディの姿が神々しく光り出すというメチャ分かりやすいサイレント映画らしい演出ですが、ある種、感動的であります。
残念なのは・・・この「港の女」の最後の巻が現存せず、スチール写真が数枚しか残っていないこと。エンディングは、残された脚本と写真からしか想像するしかないのですが、意外にあっさりとした終わり方だったような感じです。
「港の女」が制作されてから、僅か4年後の1932年・・・トーキー映画の時代となり、再び映画化されることになります。同年「グランドホテル」でスター仲間入りをしたジョーン・クロフォードが、直談判して当時所属していたMGMからユナイテッドアーツに貸し出される形(現在フィルムはMGM所有)で、主演したのが「雨/Rain」なのです。ジョーン・クロフォードとしては演技派女優として認められたいという一心だったようですが、当時はまだ技量的に厳しいものがあったようで評判は散々だったと言われています。
グロリア・スワンソンと違って・・・ジョーン・クロフォードが演じたサディは、いかにも”娼婦”というイデタチで、濃い化粧に派手な胸の開いたドレス、フィッシュネットタイツに下品なプラットフォームのパンプス、両手にはジャラジャラと腕輪を何重にもつけているという”下品”を絵に描いたような格好です。目も当てられないほどの棒読み演技で、クリスチャンとして生まれかわるのも唐突すぎる印象・・・ただ、質素で地味な姿は、ジョーン・クロフォードが本来持っている素の美しさが際立っていることは否定できません。
何故か、日本では故淀川長治氏が、ジョーン・クロフォードの代表作として本作を「淀川長治の名作100選」の一作に選んでいたこともあり、後年の「何がジェーンに起こったか?」と並んで昔から日本国内ではDVD化もされているのです。ボクのようなジョーン・クロフォードのファンには、見逃せない作品ではあるものの・・・1930年代、ハリウッド黄金時代のジョーン・クロフォードの主演作品としては、クラーク・ゲーブルとの共演作品の方がオススメであります。(めのおかし参照)
3度目の映画化は、ハリウッドで3D映画が流行していた1953年の「雨に濡れた欲情/Miss Sadie Thompson」で、3Dで制作されたのです。しかし公開時、3Dでの上映は2週間のみでアメリカで広く公開されたのは2Dバージョンが多かったそうです。(翌年の日本公開された際には2Dのみ上映)現在、Twilight Time/トワイライト・タイム(3000枚限定販売のレーベル)から復刻された3Dバージョンのブルーレイが販売(在庫限り)されています。
アクションでもなく、ホラーでもない、本作のような作品が3Dの意味ってあったの?と疑問に思ったのですが、実際に視聴してみると主演のリタ・ヘイワースの肉体の生々しさには、大きく一役かっているのです。特に、スケスケのレースのドレス姿で兵士たちの前で踊るミュージカルシーン(本作はミュージカルナンバーのあるミュージカル映画!)は、公開時には各国で上映禁止になったのも納得してしまうほど・・・本作は「醜聞殺人事件」「サロメ」に続くリタ・ヘイワース復帰3作目でもあり、当時限界ギリギリの汗ばんだ肉体のセクシーさ炸裂なのであります。
前二作では亜熱帯特有のスコール=雨が、ウェットでダークな印象を与えましたが、本作は観光映画のような鮮やかなテクニカラーとリタ・ヘイワースの明るいエロティズムで、イカニモなハリウッド映画に仕上がっています。神父が自殺するというサプライズ展開には変わりはありませんが・・・エンディングもサディがオハラ軍曹よりも先にシドニーに向かって旅立つという、ある意味”ハッピーエンド”になっているのです。
アンチ・クリスチャン的「宗教の不信」も大好物のボクにとっては、約100前に書かれたサマセット・モームの短編小説を原作とした映画3作品も、一種の”おキャンプ映画”として味わってしまうのであります。
「港の女」
原題/Sadie Thompson
1928年/アメリカ
監督 : ラオール・ウォルシュ
出演 : グロリア・スワンソン、ライオネル・バリモア、ラオール・ウォルシュ
1929年11月、日本劇場公開
「雨」
原題/Rain
1932年/アメリカ
監督 : ルイス・マイルストン
出演 : ジョーン・クロフォード、ウォルター・ヒューストン、ウィリアム・ガーガン
1933年9月、日本劇場公開
「雨に濡れた欲情」
原題/Miss Sadie Thompson
1953年/アメリカ
監督 : カーティス・バーンハート
出演 : リタ・ヘイワース、ホセ・ファーラー、アルド・レイ
1954年2月17日、日本劇場公開