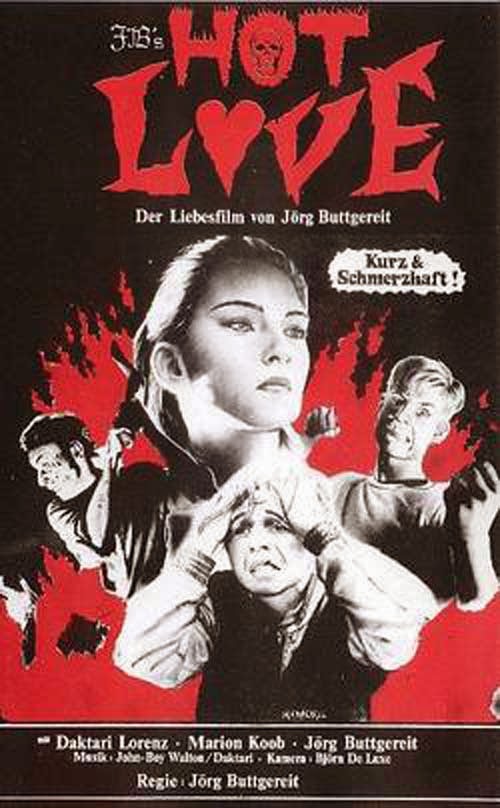去年、アメリカのケーブルテレビのHBOで制作された「Looking/ルッキング」は、サンフランシスコに暮らすアラサーとアラフォーのゲイ男性3人と彼らの恋人、友人を中心に「リアル」なゲイライフを描いたテレビシリーズであります。製作に関わっているのが、イギリスのゲイ映画「Weekend/ウィークエンド」(めのおかし参照)の監督として知られるアンドリュー・ヘイということも話題になっています。
ゲイ人権運動は日本より進んでると思われるアメリカですが・・・LGBTを主人公としたテレビドラマが制作されるようになったのは、わりと最近(1990年代末期)になってのことかもしれません。1993年製作の日本のテレビドラマ「同窓会」(めのおかし参照)がニューヨークの日本人向けチャンネルで放映された時・・・「テレビで男性同士のラブシーンが!」と日本人だけでなくゲイコミュニティーでも話題になったのも、当時のアメリカではケーブルテレビであっても、同性同士の”マジな”ラブシーンというのはタブー視されていたのです。ゲイの男性キャラクターが、テレビに登場しなかったわけではありませんが・・・あくまでもサイドキック(脇役)の道化役として笑いをとるための存在でしかなかったのですから。
全米ネットワークのひとつである”NBC”で1998年から放映された「Will & Grace/ふたりは友達?ウィル&グレイス」は、典型的なシチュエーション・コメディという枠(男2人、女2人がメインキャスト)ではあったものの、カミングアウトしているゲイ男性が主人公というのは、画期的だったと言えるでしょう。ただ、舞台となっていたニューヨークのゲイコミュニティーから強い支持を集めたとは言い難く・・・どちらかというとゲイに理解のあるストレートの視聴者にウケていた印象でしょうか。ストレートの女性とゲイの男性の友人関係に注目が集まり始めた頃でもあり、タイムリーなドラマではあったのです。
1999年にイギリスのチャンネル4で放映された「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」は、オブラートに包んでないゲイ男性を主人公にした本格的なドラマです。当時はまだ、アメリカでも、ゲイを主人公にしたテレビドラマシリーズはありませんでした。露骨なセックスシーンや、主人公のひとりが15歳という”未成年”ということも衝撃的!しかし残念ながら、当時ボクが在住していたアメリカではテレビで放映されることはなく(内容的にいうよりもイギリスのチャンネル4の番組のディストリビューターがいなかったことが理由らしい)・・・2年近く経ってからアメリカのケーブルチャンネル"SHOWTIME”でのリメイク版の放映後に、DVDで観ることになります。
ゲイタウンとして知られるマンチェスターを舞台にしたイギリス版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」の主な登場人物は・・・広告代理店で務めるモテ男スチュアート(アメリカ版ではブライアン)、ストアマネージャーでスチュアートの幼馴染みヴァンス(アメリカ版ではマイケル)、そして15歳の高校生でスチュアートに恋するネーサン(アメリカ版ではジョナサン)の3人で、彼らを取り巻くゲイの友人フィルとアレクサンダー(アメリカ版ではテッドとエメット)など、アメリカ版とキャラクターの設定は、殆ど同じです。
スチュアートがレズビアンカップルに精子提供をして子供を授かるところから物語がスタートするところ、ヴァンスの母親がゲイの息子に対して理解をしていること、アレクサンダーが日本人ハスラーに騙されるエピソードなど、アメリカ版へ引き継がれたプロットは多くあります。ただ、イギリス版は30分ほどの8エピソードのファーストシーズンと、45分ほどのスペシャル版の2エピソードのセカンドシーズンという短いシリーズで終わっており、主人公3人の三角関係を描くだけに終わっています。
本作は、幼馴染みであるスチュアートとヴァンスの友情が愛情へと変わっていくという・・・アメリカ版とは全く違う結末となっているのです。彼らの友人のひとりであるフィルは、麻薬の過剰摂取でなくなってしまいますし・・・スチュアートに振られたネーサンはスチュアートの跡を継いで(?)モテ男に成長するという展開となります。
結末は・・・アメリカのテキサス州の田舎(ホモフォビアのある保守的な地域)を車で旅しているスチュアートとヴァンス。男同士でイチャつく二人に、ひとりの田舎者が罵声を浴びせると、スチュアートは隠し持っていた拳銃で脅して、男に謝罪させるのであります。「してやったり!」と大喜びの二人の後ろ姿で終わるのですが・・・なんとも陳腐な結末ではないでしょうか?イギリス版「Queer as Folks/クィア・アズ・フォークス」は、画期的なテレビシリーズではありましたが、制作者の意識の低さも感じさせるところもあります。
イギリス版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」のイギリス国内での放映開始直後からリメイク権利を巡って、"HBO”と”SHOWTIME”のあいだで熾烈な戦いがあったそうです。1998年から”HBO”で放映されていた「Sex and the City/セックス・アンド・ザ・シティ」は社会現象になるほどの大ヒット・・・その”ゲイバージョン”としてピッタリのシリーズだったのでしょう。結果的に”SHOWTIME”がリメイク権利を獲得することになります。
当初、アメリカ版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」の舞台は、ニューヨークのマンハッタン島をハドソン川対岸に望むジャージーシティーにする予定だったそうです。ゲイカルチャーだけでなく世界の文化が集まっている大都市と川ひとつで隔てられている小都市がふさわしいと考えたようですが・・・実際にロケーション撮影されたのが、カナダのトロントということもあり、街並の印象が似ているニューヨーク州ピッツバーグに変更となったとのこと。ピッツバーグは、別にゲイの街として知られているわけではないし・・・さびれた地方都市というイメージしかなかったので、舞台がピッツバーグというのには違和感を感じたものです。
配役については、ゲイ視聴者からは共感を得られなかった印象があります。まず、ピッツバーグ一番のモテ男で誰もがエッチしたいと思っているという(かなりハードルの高い役柄!)ブライアンを演じたゲイル・ハロルドは、ストレートの世界ではセクシーでハンサムな色男なのかもしれませんが・・・ゲイの世界では、それほど人気のあるタイプではありません。誰もがブライアンとエッチをしたがるという設定には、ゲイ視点では「ありえない」と思ったものです。ブライアン以外のゲイの登場人物も少々クリーンカット過ぎで、マッチョ、髭、クマ系、刺青・・・といった”ゲイ”が存在しなかったことも、ストレートの視聴者向けという印象は拭えません。さらに、登場人物の誰もが”セックス依存症”なのではないかと思うほど、やりまくりというのも、偏ったステレオタイプという感じでした。
マイケルを演じたハル・スパークスのキャスティングに関しては驚きではあったものの、ゲイの視聴者からはウェルカムだった気がします。VH-1というミュージックチャンネルで「TALK SOUP/トークスープ」(その日のトークショー番組の面白い部分を集めてつっこむというコメディ番組)のホストをしていて、結構売れ始めていたハル・スパークスは、まさに「アメリカン・ボーイ」のステレオタイプで、ゲイの一部には、すでに結構人気があったのです。また、ゲイの息子に理解のあるマイケルの母親デビーを演じたシャロン・グレスは、1980年代に放映された「女性刑事コンビの活躍を描いたキャグニー&レイシー」のキャグニー役で知られていて、レズビアンを中心にLGBTコミュニティーから絶大な人気を誇っていた”男前”な女優さん・・・ここはツボをおさえたキャスティングはあったわけです。
物語の発端や登場人物たちの設定は、イギリス版と同じですが・・・アメリカ版はシーズン1だけでも60分ほどのエピソードが22話(シーズン5で合計83話)もあり、シーズン1前半から脇役の伏線のエピソードを膨らましたアメリカ版のオリジナルのプロットがでてきます。ブライアンの精子提供で子供を授かったレズビアンカップルのリンジーとメラニーのゲイ両親としての生活、完全に脇役扱いだったテッドやエメットの恋愛と転落、ブライアンに恋してしまう17歳(イギリス版の15歳から変更)の少年ジャスティンの母親の葛藤など・・・イギリス版では十分に描かれることのなかった主人公たちを取り巻く人物を深く描いていくことになっていったのです。
2000年前後というのは、1980年半ばからゲイコミュニティーを苦しみ続けたエイズの治療方法が確立し始めた頃・・・過激なエイズ撲滅のための政治運動も一段落して、再びフリーセックス時代への憧れさえ芽生え始めてきた時代でした。1960年代後半から1970年代のスタイルが再流行していたこともあり、アメリカ版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」は、ミュージックビデオ的なザッピングを多用した演出や、サイケデリックなクラブシーンは派手でイケイケな雰囲気に満ちています。イメージとしての1970年代から1990年代までのゲイカルチャーをミックスしたような世界観に、それらの時代を体験してきたボクの世代には懐かしささえ感じさせたものです。
ゲイ向けテレビチャンネルではなく・・・”SHOWTIME”という一般の視聴者向けチャンネルで唯一のゲイを主人公の連続ドラマという存在であった「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」には、LGBTコミュニティーが抱える社会的な問題を扱っていくことが使命のようなところがあったのかもしれません。徐々にアメリカ版はイギリス版よりも、政治的なメッセージも訴えかけていくことになっていきます。ゲイであることを理由のイジメや差別、ゲイ両親が向き合わなければいけない問題、麻薬やセックス依存、当時アメリカでは合法化されていなかった同性婚についても描かれており、その後アメリカのいくつかの州で同性婚を認める動きになっていったのには、このドラマの存在が無関係ではないかもしれません。
放映開始された頃には、ゲイ版「Sex and the City/セックス・アンド・ザ・シティ」と呼ばれていましたが、登場人物たちの年齢や世代的に直面する問題は「Thirtysomething/ワンダフルサーティーズ」に近いような気もします。LGBTコミュニティーだけでなく、愛情、友情、裏切り、和解など、物語を紡いでいくのは、まさにアメリカのテレビドラマシリーズの独壇場・・・ゲイの登場人物だけでなく、周囲の人々や家族をも巻き込んで、壮大なドラマとなっていくのです。シーズンを重ねていくにつれて、登場人物のキャラや物語の統合性を失ったりもすることはありますが、思いがけない展開により心を鷲掴みにされてしまうのも、アメリカのテレビドラマシリーズの得意とするところかもしれません。
アメリカ版は、元ネタのイギリス版とは、全く違うエンディングを迎えます。すでにブライアンとマイケルの友情以上恋人未満の関係を描く物語ではなくなっていますし、マイケルはベンとの同棲関係に落ち着いてからというものドラマの中での存在感は薄くなっていて、群像劇の中の登場人物のひとりでしかありません。結局、ブライアンとジャスティンの(当時はまだ非合法でしたが)同性婚で結ばれるという着地点に、落ち着くことになります。
アメリカ版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」は、ゲイのライフスタイル(ステレオタイプの偏りがあるものの)をエンターテイメントとして描くこと、そして、LGBT視点で政治的に正しいことを訴えたエポックメイキングのドラマシリーズであったことには違いありません。
「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」の後、「Lの世界」というレズビアンドラマはありましたが、ゲイ(男性)を主人公とした連続ドラマは、2014年1月にスタートする”HBO”の「 Looking/ルッキング」が始まるまでなかったそうです。確かに、ゲイのキャラクターは多くのドラマでも見かけるようにはなったのもの(日本のドラマでも近年オネエキャラは増えた)・・・ゲイを主人公にした連続ドラマは、あくまでも「特殊なジャンルもの」であり、常にどこかでチャンネルで制作されているわけではなのかもしれません。
「 Looking/ルッキング」のクリエーターのひとりは、イギリスのゲイ映画「Weekend/ウィークエンド」のアンドリュー・ヘイ監督・・・狭い焦点によるボケ感と極端なクロースアップにより、登場人物の心情を伝えるパーソナルな演出が高く評価されました。本作でも、テレビっぽい照明を使わずに、映画っぽい画面作りをしています。また、イギリスのテレビドラマのフォーマットと同じく、ワンシーズンが30分ほどの8エピソードで構成され、イギリス版「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」と同じフォーマットで製作されています。
さらに、キャストの多くはイギリスで活動している俳優だったりと、アメリカのテレビドラマでありながら、イギリス映画界の遺伝子を強く引き継いでいるのです。「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」に続き「 Looking/ルッキング」も(基本的に)イギリス生まれというのは偶然ではなさそう・・・アメリカのエンターテイメント界で、ゼロからゲイドラマを製作するのは、いまだに壁があるということかもしれません。
アメリカの大都市名の中でもゲイの人口に比率が多い(ゲイの総人口数だとニューヨーク?)サンフランシスコを舞台にしている「 Looking/ルッキング」は、ロケーションもサンフランシスコの街中ということもあり「ゲイのリアルな日常」を描くのが”売り”であります。
主人公は、ゲームデザイナーとして働く29歳のパトリック(ジョナサン・グロフ)、アーティストのアシスタントとして働いていた31歳のオーガスティン(フランキー・J・アルヴァレズ)、自分のレストランを開店しようとしている39歳のドム(マウリー・バレット)の3人・・・リアルにゲイらしい配役は、好感が持てます。
パトリックは、アメリカのアラサーゲイの平均な”ボーイ・ネクスト・ドア”(隣に住んでそうな男の子)のキャラクター・・・恋愛相手がラテン系というところが、まさに「あるある」で、ここ近年はアメリカ白人とラテン系という組み合わせのカップルは東海岸でも西海岸でも多いようです。性格的に「コレ」といった特徴もなく、たいして興味深くない人物像のパトリックが、主人公3人の中でもメインキャラクターというところが、本作の”ミソ”のような気がします。
オーガスティンは無精髭を生やしたアート系のゲイ・・・近年、キレイに整えた髭よりも無精っぽい髭の方が若い世代のゲイにはポピュラーのようで、彼のようなむさ苦しいタイプのアラサーゲイは多かったりします。また、アート系のオーガスティンにはアフリカ系(黒人)の恋人がいるのですが・・・これもまた「あるある」です。クリエーターの白人ゲイは、ラテン系、アフリカ系、またはアジア系の男性とくっつくことが多かったりするのです。
一番年長のドムは、往年の”クローン”を彷彿させるようなスレンダーな筋肉質の体型に、整えられた口髭のダディータイプ・・・長年、洒落たレストランでウェイターとして働いているという設定も、まさに「あるある」です。ルームメイトとして一緒に暮らしているのが、高校時代の元彼女ドリス(ローレン・ウィードマン)というところも、結構ありがち・・・。ドリスは、今でも密かにドムのことを男性として意識していることは言うまでもないでしょう。(涙)
性格もライフスタイルも違う彼ら3人が親友という設定には、正直、頭をひねってしまうところはありますが・・・3人に共通しているのは、どこかしら”ウジウジ”しているところ。
パトリックは恋人のリッチー(ラウル・カスティロ)に上手く気持ちを伝えられなかったり、上司のケヴン(ラッセル・トヴェイ)から肉体関係を求められると断れなかったり・・・自分の気持ちに正直なのか、自分の意志をハッキリ持てないのかよく分かりません。ちなみにキャストの中で一番人気(?)なのは、ケヴンを演じるラッセル・トヴェイ・・・耳の大きな特徴的なルックスとイギリス訛りで、ゲイ視聴者を虜にしています。上司でありながら・・・パトリックを誘惑しちゃう場面に”胸キュン”です。
オーガスティンは、恋人のフランク(O・T・ファグベンル)とのセックスライフを豊かにするために、ハスラーを雇って3Pセックスをするのだけど・・・そうして彼がそんなことをするのかが、よく分かりません。ドムは、レストラン開店のビジネスパートナーでもある50代のリン(スコット・バクラ)に、次第に心惹かれていっているのだけど、それは父親に対する甘えのようなものなんのか、単なる肉体的な欲望なのか、よく分かりません。意志を持って行動したり発言するのは、主人公3人ではなく、彼らを取り巻く人たちことが多い気がするのですが・・・受け身なキャラクターの方が、視聴者の共感を得やすいってことなのでしょうか?
パトリックは恋人のリッチー(ラウル・カスティロ)に上手く気持ちを伝えられなかったり、上司のケヴン(ラッセル・トヴェイ)から肉体関係を求められると断れなかったり・・・自分の気持ちに正直なのか、自分の意志をハッキリ持てないのかよく分かりません。ちなみにキャストの中で一番人気(?)なのは、ケヴンを演じるラッセル・トヴェイ・・・耳の大きな特徴的なルックスとイギリス訛りで、ゲイ視聴者を虜にしています。上司でありながら・・・パトリックを誘惑しちゃう場面に”胸キュン”です。
オーガスティンは、恋人のフランク(O・T・ファグベンル)とのセックスライフを豊かにするために、ハスラーを雇って3Pセックスをするのだけど・・・そうして彼がそんなことをするのかが、よく分かりません。ドムは、レストラン開店のビジネスパートナーでもある50代のリン(スコット・バクラ)に、次第に心惹かれていっているのだけど、それは父親に対する甘えのようなものなんのか、単なる肉体的な欲望なのか、よく分かりません。意志を持って行動したり発言するのは、主人公3人ではなく、彼らを取り巻く人たちことが多い気がするのですが・・・受け身なキャラクターの方が、視聴者の共感を得やすいってことなのでしょうか?
「 Looking/ルッキング」は「Weekend/ウィークエンド」のように、おしゃれ感が溢れる映像です。サウンドトラックの選曲や引用も心憎いほど!ただ、ワンシーズンが30分の8つのエピソードなので「尺」としては2時間スペシャルの2エピソードぐらい・・・シーズン2、シーズン3と重ねるごとに、それぞれのキャラクターが深く描かれていくのだとは思いますが、物語のテンポもゆっくりなので、ワンシーズンを見終わっても映画一本で描けるぐらいの内容ではあります。ただ、近年のアメリカの連続テレビドラマは、ドラマテックな展開で目を離せないというだけでなく・・・ドラマの”世界観”や”空気感”を楽しむという傾向もあるようです。
「リアル」の表現に於いて・・・テレビドラマというメディアは「YouTube」を超えることはできないことも、今の現実かもしれません。ウィル(Will)とアール・ジェイ(RJ)の20代のゲイカップルが「shep689」のアカウント名で、2012年1月1日から、ほぼ毎日アップしている動画ブログ「A GAY IN THE LEFE」というのがあるのですが・・・これは、まぎれもなくゲイの「リアル」な日常を映し出しているのであります。
あまりに普通過ぎる彼らの日常に多くの人が親しみ覚えると同時に、ある意味、ちょっと退屈さを感じるかもしれません。典型的なアメリカ白人のメガネ君「ウィル」と、ちょっとワイルドなラテン系でひょうきんな「RJ」が、カメラとの相性の良いルックスというのも人気の要因のひとつではありますが・・・日常から垣間見れる真摯な人間性が、視聴者を虜にしているのだと思います。本物の人生の一瞬一瞬の積み重ねは、テレビドラマの「リアル」を、あっさりと超えてしまうのです。
今のゲイライフを「リアル」を描こうとしている「 Looking/ルッキング」が、少々退屈に感じられるのも、当然といえば当然ことなのかもしれません。「リアル」な日常なんて、テレビ用にドラマチックな演出がなされているわけではないのですから。振り返ってみた時に初めて何かに気付くことがあるように・・・「 Looking/ルッキング」は、繰り返し視聴して噛めば噛むほど味が出てくるような気がします。15年前に制作された「Queer as Folk/クィア・アズ・フォーク」のように、政治的メッセージを訴えたり、LGBTであることでドラマを生んだりする時代は、とっくに終わったということなのです。
「 ルッキング」
原題/Looking
2014年~/アメリカ
制作総指揮 : アンドリュー・ヘイ、デビット・マーシャル・グラント、サラ・コンドン
原作 : マイケル・ランナン(HBO「Lorimer」)
出演 : ジョナサン・グロフ、フランキー・J・アルヴァレズ、マウリー・バレット、ローレン・ウィードマン、ラウル・カスティロ、ラッセル・トヴェイ、O・T・ファグベンル、スコット・バクラ
”HBO”にて放映
2016年12月23日より”Hulu”にて配信
「クィア・アズ・フォーク」(アメリカ版)
原題/Queer as Folk
2000年~2005年/アメリカ、カナダ
制作総指揮 : トニー・ジョナス
制作 : ケヴィン・インチ、シーラ・ホッキン
出演 : ゲイル・ハロルド、ハル・スパークス、ピーター・ペイジ、スコット・ローウェル、ミシェル・クラニー、テア・ギル、
”SHOWTIME”にて放映
「クィア・アズ・フォーク」(イギリス版)
原題/Queer as Folk
1999年~2000年/イギリス
制作総指揮 : ニコラ・シンダー
原作/制作 : ラッセル・T・デイヴィス
出演 : エイダン・ギレン、クレッグ・ケリー、チャーリー・フーナン
”Chennel 4”にて放映