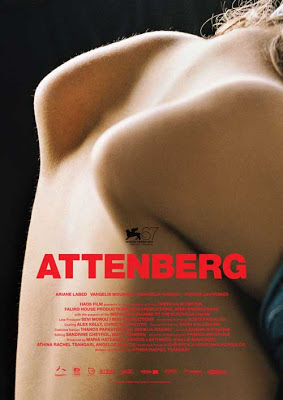ジョーン・クロフォードという女優にボクが興味を持ったのは、1981年にアメリカで公開された「愛と憎しみの伝説/Mommie Dearest」というフェイ・ダナウェイがジョーン・クロフォードを演じた映画でした。養女によって暴露された継母の私生活は、彼女の50年近い女優としての栄光を打ち砕いてしまうほど致命的でありました。エイドリアンによる肩パッドの入った衣装と太い眉と真っ赤な口紅のメイクが印象的なハリウッドスター女優のひとりでだという程度の知識しかなかったボクのようなリアルタイムで彼女を知らないファンにとっては、ある種のカルト的なイメージを永遠に植えつけることとなったのです。
1962年に公開された「何がジェーンに起ったか?」の大ヒット以降、往年のベテラン女優が醜悪な老女役を演じる「サイコ・ビディ/Psycho-biddy」と呼ばれる一連のサイコホラー作品が作られるようになるのですが・・・「血だらけの惨劇」は、上映館の座席に電気ショックの装置を取り付けたり、ガイコツの人形を浮かばせたり、エンディングが怖くて観れなかったら入場料払い戻しなどなど、子供騙しのような”仕掛け”を売り物にしてヒット作を生んできたギミック映画の帝王と呼ばれていたウィリアム・キャッスル監督が、満を持してA級スターであるジョーン・クロフォードを主演に迎えて製作した意欲作であります。ジョーン・クロフォードは「何がジェーンに起ったか?」のロバート・アルドリッチ監督による「ふるえて眠れ」への出演をベティ・デイヴィスと共にオファーされていたそうなのですが「もうベティとの共演は懲り懲り」と断り・・・「不意打ち」の出演オファーも「もう閉じ込められる役はもうやりたくない」と蹴ったそうです。結局「ふるえて眠れ」と「不意打ち」のどちらも、ジョーン.クロフォードの代わりにオリヴィア・デ・ハヴィランドがキャスティングされました。
ジョーン・クロフォードが、これらの「サイコ・ビッディ」への出演オファーを蹴ってまで、この「血だらけの惨劇」の出演を決めた理由として・・・B級映画監督のウィリアム・キャッスルが、ジョーン・クロフォードを「スター女優」として特別待遇してまで出演を懇願したということがあるのかもしれません。彼女専用の楽屋には、バーボンとキャビアを常に用意させ、専属のコスチューム、専属のアクセサリー、専属のヘアメイクは勿論のこと、カメラマン、脚本、演出、配役まで口を挟むことを許されていたそうです。実際、娘役は元々セクシーな若手女優が演じるはずだったのですが、ジョーン・クロフォードの意向で、過去に共演したことのある地味なダイアン・ベイカーに変更されています。また、医者を演じたミッチェル・コックスは、彼女が副社長をしていた”ペプシ・コーラ”の重役のひとりの素人さん・・・彼の要望に応えるために、彼女の口添えでキャスティングされました。さらに、彼女が撮影現場に到着する時には、すべての出演者と撮影スタッフがお迎えしなければならなかったり、すでに彼女の肌の張りを保つために、撮影セットは常に凍えるほど低い温度に設定されていたそうです。
常にヒッチコックを意識していたウィリアム・キャッスル監督は「サイコ」の原作者であったロバート・ブロックを脚本に起用します。それでも”ウィリアム・キャッスル”は”ウィリアム・キャッスル”・・・子供騙しの悪趣味な演出には変わりなく、ジョーン・クロフォードの熱の入った過剰な演技と相まって、本作は一連の「サイコ・ビッディ」作品の中でも、低俗さが際立つ”素晴らしい”怪作となっているのであります!ちなみに原題の「Strait-Jackest」というのは、手の自由がない「拘束服」のこと・・・今では、テロリストが人質の移送ぐらい(!?)でしか使われない非人道的な代物です。
今から20年前、ルーシー(ジョーン・クロフォード)は、浮気して寝入っていた年下の夫フランク(リー・メジャース)と浮気相手の元カノを「斧」で首を切り落として殺害してしまいます。その一部始終を、幼い娘のキャロルは目撃してしまっていたのです。状況的には明らかな”意図”をもった”殺人にか思えないんだけど・・・浮気現場を目撃して気が狂って殺人を犯したということになり、ルーシーは精神病院に収監されることになるのです。この事件を起こしたとき、映画の中での設定ではルーシーは「29歳」・・・それを60歳のジョーン・クロフォードが演じているんですから、かなり無理があります。ジョーン・クロフォードのトレードマークの髪型、太い眉、大きな唇に、派手なプリントのドレスとジャラジャラと付けたイカニモ安っぽいバングル・・・どう見ても”場末の女”にしか見えません。これって・・・ジョーン・クロフォード自身が女優としての全盛期(1930年代)に演じていた男を手玉に取って成り上がっていくという女性像の”パロディ”のようでさえあります。
キャロル(ダイアン・ベイカー)はルーシーの兄夫婦(リーフ・エリクソン、ロチェル・ハドソン)引き取られて、田舎の農場で育てられました。地元の名士で金持ちであるフィールド家の息子マイケル(アンソニー・ヘイズ)と、結婚を前提に付き合う若い女性に成長しています。そして、20年間の精神病院での治療を終え、ルーシーは兄夫婦の農園に戻ってくることになっているのです。20年ぶりに再会する母と娘・・・ルーシーは白髪まじりで地味なダークグレーのアンサンブルに身を包む年相応(設定では49歳ぐらい)となっています。上品な初老の女性になったルーシーは、事件前と同じ女性とは思えないほど・・・ルーシーからは事件のトラウマからは完全に抜け出していない様子もうかがえます。彫刻家となったキャロルの工房で彫刻ナイフや、事件の際に身につけていたジャラジャラ音のなるバングルに、異様な反応をしたり、殺した旦那と元カノの生首が枕元に現れる(!)悪夢にもうなされいてしまっているのですから・・・。
キャロルが、精神病院から帰宅した日のうちに、婚約者であるマイケルを紹介しようとするというのも、いくらなんでも配慮に欠けていると思うのですが・・・案の定、ルーシーはマイケルとは会わずに姿を消してしまいます。洒落っ気もないからマイケルに会いたくないんだろうと勝手に察したキャロルは、翌日、ルーシーを街に連れ出して、ワードローブ一式と、美容室でカツラを奨めるのですが・・・コーディネートしたスタイルが、殺人事件を起こした夜と殆ど同じというのが、まるで忘れたい過去を蒸し返してしまいそうで・・・かなりヤバいです。20年前と殆ど変わらない姿となったルーシーは、精神病院で過ごした20年間の時間を埋め合わせてしまったかのように、いきなり場末のズベ公に豹変・・・娘の婚約者のマイケルに色仕掛けで迫るという、痛々しさを見せつけます。
ルーシーを20年間診ていた精神科の医者(ミッチェル・コックス)が、いきなり農場を訪ねてきます。平常心を装うとするルーシーですが、明らかに不可解な行動や発言を繰り返し・・・「毎日、何をして過ごしているの?」と尋ねられて「あみもの」とポツリと返答するジョーン・クロフォードの演技は、上手い下手を超越した「怪演」であります。医者はルーシーが再び狂い始めているのではないかと疑問を持ち始めます。そこでキャロルと話をしようと、農園の納屋に入るのですが・・・いきなり斧を持った”何者”かに首を切られて殺されてしまうのです!その後、医者が乗ってきた車に気付いた農園の手伝いのレオ(ジョージ・ケネディ)も、首を切られてあっさりと殺されてしまいます。
そんな惨劇が起こっているにも関わらず、キャロル、ルーシー、兄夫婦の4人は、婚約者マイケルの実家に訪問する予定となっています。ルーシーは、まだ精神的に不安定だからと躊躇するのですが・・・キャロルが強引な求めに応じてルーシーは渋々同行させられてしまうのです。地味な年相応なダークグレーのアンサンブルの方が、娘の婚約者の両親に会うのには適していると思うのですが・・・ルーシーは派手なプリントのドレス、昔の髪型のカツラにジャラジャラとしたバングルという”場末の女”風のファッションに再び身を包んでいきます。実は婚約というのは本人同士の話だけで・・・マイケルの両親(特に母親)はキャロルとの結婚を許してはいません。勿論、理由は母親であるルーシーの過去・・・持病のために静養所に20年間いたという話を胡散臭く感じていたのです。
過去を問いただされてルーシーは真実を自ら暴露してしまいます・・・本当は20年間精神病院にたことを。そして、母親として娘キャロルの幸せを阻むものは許さないと震える声で訴えるのです!この場面でのジョーン・クロフォードの演技は大袈裟ではありますが、精神的に崩壊する瀬戸際であっても、娘の幸せを望む母親の愛情を強く心に訴えてくる名(迷?)演技なのであります。取り乱して婚約者の実家を飛び出すルーシー。その夜はお開きとなり、キャロルや兄夫婦は帰路につくのですが、ルーシーは行方知らずのまま・・・マイケルの実家の寝室では彼の父親が、寝室のクローゼットの中で首を斧で切られて殺害されてしまいます。
ここから本作のネタバレを含みます。
マイケルの母親までをも殺そうとする殺人者は、キャロルだったのでした。謝罪のために再びマイケルの実家を訪れたルーシーによって、ルーシーと同じドレスとカツラを付けた上に、顔にはルーシーの顔をかたどったゴム製のお面を付けていたのです。彫刻家であるキャロルは、母親の頭像からお面の型を取っていました。自分とマイケルの結婚を阻む者を消すために、夫殺しという過去を持った母親が再び狂ったことにして、殺人罪の罪をかぶせようとしていたのです。母親を憎みながらも、愛情に飢えていたキャロルは、遂に発狂してしまいます。歴史は繰り返す・・・とでも言うのでしょうか?
実はこの場面・・・「愛してる!」「憎んでる!」と繰り返しながら、母親のお面を握る潰すという熱演で終わるはずだったのですが、ジョーン・クロフォードが自分以外の人物のクライマックスを許すわけはありません。彼女は撮影現場で勝手に、玄関の外で柱にしがみつきながら泣き崩れる・・・という劇的なシーンを付け加えさせたのです。最後は、兄に事件の経緯を説明し、キャロルが使ったトリックを解説するほど、正気を取り戻したルーシーの姿があります。夫殺しの母親ルーシーとと同じように精神病院に収監されることになったキャロル・・・ただ、ルーシーにしてもキャロルにしても、自分の感情や利益のために犯した殺人なんだから、本来は罪に問われるべきなのですが、「狂気の沙汰」で片付けてしまうところは、精神の病気が認識され始めた1960年代という時代だったのかもしれません。
「娘は今、私を必要としている」とルーシーが語って、キャロルを見守ることを仄めかして終わる本作・・・母親の愛情の深さを印象づけるという”お仕着せがましさ”というのは、その後、私生活での鬼のような母親っぷりを暴露されたことを考えると、正直、複雑な気持ちにさせられます。「何がジェーンに起ったか?」の成功によって、気の狂った大袈裟な演技で”あれば、あるほど”観客にウケるという流行が生んでしまった「サイコ・ビッディ」の金字塔とも言える「血だらけの惨劇」。ジョーン・クロフォードの”スター女優”としての強かさを見せつけられ・・・ボクが心から愛して止まない作品のひとつなのです。