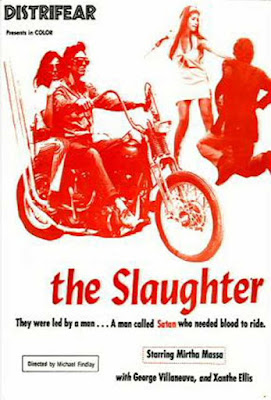15歳のとき、ボクはリバイバル上映されていた「欲望という名の電車」を映画館で観て、主人公のブランチ・デュボアというキャラクターの虜になってしまいました。原作の戯曲を繰り返し読んで、ブランチになりきって(!)ひとり芝居をしていたほどです。
何故、15歳の少年がブランチと同化しまうのか、当時は全く自分でも分からなかったのですが・・・精神的に不安定な中年女性に共感してしまうゲイのビョーキの一種だったことに次第に気付いたのは、ずっと後のことだったのです。このことは、以前「おかしのみみ」というブログに書いた記事があるので、そちらも閲覧してみて下さい。
何故、15歳の少年がブランチと同化しまうのか、当時は全く自分でも分からなかったのですが・・・精神的に不安定な中年女性に共感してしまうゲイのビョーキの一種だったことに次第に気付いたのは、ずっと後のことだったのです。このことは、以前「おかしのみみ」というブログに書いた記事があるので、そちらも閲覧してみて下さい。
ボクは映画は繰り返して何度も観ていますが、舞台は1980年に日生劇場で杉村春子がブランチを演じた公演を一度観たっきりなのです。当時、74歳だった杉村春子の迫真の演技に引き込まれて、非常に衝撃を受けたことを覚えています。共演者のキャスティングも(今、思うと)かなり豪華で・・・スタンリー役に江守徹、ステラ役に大地喜和子 ミッチ役は北村和夫(スタンレー役を長年演じていた)でした。
その後、舞台を観る機会があったのが、ニューヨークに住んでいた1992年・・・ブランチ役ジェシカ・ラング、スタンレー役アレック・ボールドウィンで「欲望という名の電車」がブロードウェイで期間限定で公演された際、チケットを購入していたのですが・・・ちょうど公演日にグリーンカードの面接(日本で行なわれた)が組まれてしまい、泣く泣く諦めた経緯があるのです。ちなみに、この二人主演でテレビムービー版が1995年に制作されています。
友人から、シアターコクーン・オンレパトリー2017 DISCOVER WORLD THEATRE VOL.3「欲望という名の電車」の初日の招待券を頂くことになって、人生で二度目の「欲望という名の電車」の観劇となった次第です。招待券を頂いておいて・・・辛口の感想を書くのは大変気が引けるのですが、ここから書くことは「欲望という名の電車」に取り憑かれた頭のおかしなゲイの戯言だと思ってください。
今回の「欲望という名の電車」のキャスティングについては、正直、首を傾げてしまうところがあります。
ステラ役を演じる鈴木杏は年齢的にまだ若くて(と言っても30歳だけど)、ポーランド系の肉体労働者の男の性的魅力に堕ちてしまった元上流階級の女性を表現することが出来るのかなという感じです。
ミッチ役を演じる藤岡正明は、あまりにも若くてハンサムすぎで絶対アリエナイ・・・台詞にもあるように、ミッチは大柄でガッチリ体型の中年男という役柄で、そんなパッとしない男がブランチの王子さまとなるのがミソなのですから。
ボクが受け入れるのに苦しんだのが、ブランチを演じる大竹しのぶであります。映画でブランチを演じたヴィヴィアン・リーのイメージが強いということがありますが・・・大竹しのぶの身体的特徴が、どうしても華奢なブランチのイメージには繋がらないのです。
ステラ役を演じる鈴木杏は年齢的にまだ若くて(と言っても30歳だけど)、ポーランド系の肉体労働者の男の性的魅力に堕ちてしまった元上流階級の女性を表現することが出来るのかなという感じです。
ミッチ役を演じる藤岡正明は、あまりにも若くてハンサムすぎで絶対アリエナイ・・・台詞にもあるように、ミッチは大柄でガッチリ体型の中年男という役柄で、そんなパッとしない男がブランチの王子さまとなるのがミソなのですから。
ボクが受け入れるのに苦しんだのが、ブランチを演じる大竹しのぶであります。映画でブランチを演じたヴィヴィアン・リーのイメージが強いということがありますが・・・大竹しのぶの身体的特徴が、どうしても華奢なブランチのイメージには繋がらないのです。
昔、ボクが持っていた大竹しのぶのイメージというのは・・・「事件」や「あゝ野麦峠」で数々の演技賞を総なめにした演技のすごく上手い若手女優、素顔は田舎臭い天然系というイメージで、当時の好感度は決して低くはありませんでした。しかし、その後、大竹しのぶは数々の男性遍歴と多くのスキャンダルにまみれて”魔性の女”と呼ばれるようになっていきます。そして、演技派女優として年齢を重ねていくうちに、すっかり”大御所”という芝居が上手いことが前提の存在になっていったのです。
2009年に、ブロードウェイミュージカル「グレイ・ガーデンズ」の日本人キャスト版を、ボクは観劇しているのですが・・・大竹しのぶは、ジャクリーン・オナシス・ケネディの従姉でボロボロの豪邸で母親とと二人で暮らしていた実在した女性を演じていました。狂気の中にも上流階級出身の品性を感じさせるべき役柄なのにも関わらず、大竹しのぶはどうしても庶民臭が抜けず、ただただ”下品”なだけ・・・母親役を演じていた草笛光子が、どんなに髪を振り乱しても凛とした上品さを失わないオーラを発していたのとは大違いでした。どれほど演技が上手くても、品性を演じることはできないものだと感じさせられたものです。
テレビのバラエティ番組では、相変わらず甘ったるい天然系のイメージの大竹しのぶですが・・・演じる役柄は”魔性の女”のタイプキャスティングで、下品な中年女役ばかりをやっている印象しかありません。当然、与えられた役柄を素直に演じているだけだと思いますが・・・ゲッソリするほどゲスく演じるので(ある意味、褒め言葉?)大竹しのぶの演技を見かけるたび、胸くそが悪くなるようになってしまったのです。
2002年5月に、蜷川幸雄演出で大竹しのぶがブランチ役を演じた「欲望という名の電車」が公演されていたようなのですが、この公演は、ボクは完全にスルーでした。ステラ役には寺島しのぶ(!)、スタンレー役に堤真一、ミッチ役に六平直政というキャスティングで、非常にソソられるところがあります。また、あの蜷川幸雄が、どんな「欲望という名の電車」を演出していたのかも大変気になります。
ブランチ役というのは女優にとってチャレンジしてみたい役柄のひとつではあるようで・・・杉村春子没後には、浅丘ルリ子(舞台を日本に置き換えた)、篠井英介(世界で初めて女形で演じた)、水谷良重、岸田今日子、東恵美子、樋口可南子、高畑淳子と「なるほど〜」と唸ってしまうような名前が連なっています。そういう蒼々たるメンバーの中で、別な演出家によるプロダクションでブランチ役を二度も演じるのは、大竹しのぶが初めてかもしれません。
さて、今回の「欲望という名の電車」は、演出がフィピップ・ブリーン(Phillip Breen)で、美術や音楽もイギリス人スタッフによるものとなっています。中心となるスタッフがイギリス人ということが関係しているのかは分かりませんが・・・海外戯曲ものを日本人キャストで演じるとき、大袈裟な手振り身振りの”ベタ”なジャスチャーを交えて”外人”になりきろうとする傾向って、日本演劇界にはあるように思うのですが、本公演では、わざとらしいジャスチャーはありません。マシンガンのように早口で飛び交う台詞をやり取りしている時も(山場となる感情が高ぶるような場面以外)イスに座ったままだったり、立ったままだったりと・・・まるで歌舞伎のお芝居のようなのです。
舞台上には、ステラとスタンレーのアパートメントの2部屋が、リアルな家具や調度品と共に再現されていますが、2階への階段はなく・・・2階へは、舞台に向かって左側の舞台袖にはけるという演出になっていました。スタンレーの暴力やブランチへの仕打ちに我慢できずに、ステラが逃げる先が物理的に住んでいる場所より「上」の2階というところに意味をボクは感じていたので、本公演の装置はちょっと意外でした。
第1幕ではリアルに再現した部屋であるのが、ゴチャゴチャしていて芝居をこじんまりとさせてしまっているように感じたのですが・・・第2幕でブランチの幻覚や妄想が舞台奥に現れて、アパートメントの部屋の現実との比較が明確になることで、あえてリアルな部屋を再現していることが腑に落ちました。印象に残った音楽の使い方としては、場面が変わったり時間経過を表す暗転してる時のジャズ音楽で、ブランチの精神の崩壊していくにしたがって、旋律やリズムが乱れていくところが効果的だったように思います。
スタンレー役の北村一輝は、見た目が”濃い”という意味では役柄にハマっていたとは思うのですが・・・ただ、それだけで一般的なスタンレーらしさをそつなくこなしていた印象でした。ミッチ役の藤岡正明のミスキャストは、最後まで違和感は拭えませんでした。興行的なことを配慮してのキャスティングだったのかな・・・と思ってしまうほど。鈴木杏からは、スタンレーの動物的なセックスに魅せられているセクシャリティを表現しきれず、ブランチとスタンレーの狭間で苦悩するさまも感じられず、ただただスタンレーのDVに耐えているようにしか思えません。
エンディングの演出で気になったのは、ステラがブランチを見送り立ちすくむ”だけ”で終わってしまったところ。「もう二度と家には戻らない!」と、これまでのスタンレーの横暴に堪忍袋の緒が切れたステラが2階へ駆け上がり、ステラの名を絶叫し続けるスタンレーの姿で終わるはずなのですが・・・今回は2階へ続く階段がない舞台装置なので、ステラが立ちすくんで暗転という演出にしかできなかったのでしょうか?
なんとも尻切れトンボな終わり方で・・・ブランチを精神病院送りにしたスタンレーを、ステラが受け入れてしまっているようにしか解釈できなくて、原作とは真逆であるような印象さえ持ちました。
エンディングの演出で気になったのは、ステラがブランチを見送り立ちすくむ”だけ”で終わってしまったところ。「もう二度と家には戻らない!」と、これまでのスタンレーの横暴に堪忍袋の緒が切れたステラが2階へ駆け上がり、ステラの名を絶叫し続けるスタンレーの姿で終わるはずなのですが・・・今回は2階へ続く階段がない舞台装置なので、ステラが立ちすくんで暗転という演出にしかできなかったのでしょうか?
なんとも尻切れトンボな終わり方で・・・ブランチを精神病院送りにしたスタンレーを、ステラが受け入れてしまっているようにしか解釈できなくて、原作とは真逆であるような印象さえ持ちました。
ブランチ役の大竹しのぶについては、やはり「女優”大竹しのぶ”」の底力を見せつけられた気がします。舞台女優としては当然のことのかもしれませんが・・・叫び狂う台詞も、ささやくような台詞も、マシンガンのように畳み掛けるような台詞も、しっかりと言葉のひとつひとつが意味を持って伝わってきて、他の役者たちとの技術な差を見せつけていました。
本作で最も有名なのは、精神病院の迎えにきた医者が紳士らしい振る舞いで差し出した腕に、淑女のように手をかけるブランチが言う台詞「どなたかは存じ上げませんが、わたくしは見知らぬ方のご親切を頼りにして参りましたの」だと思うのですが・・・本公演では、意外なほどサラッと流してしまっていたので、ちょっと腰砕けでした。もっともっと溜めて言って欲しい・・・(ボクにとっては)重い重い台詞なのです。
舞台では、役柄の身体的特徴と演じる役者が一致しなくても良いという考え方もあるのかもしれませんが・・・ミッチがブランチを持ち上げて「羽根のように軽い」という台詞があるので、ブランチが今にも崩れてしまいそうなほど華奢であることは必須のはず。大竹しのぶが持ち上げられるシーンでは、思わずボクは心の中で苦笑いをしてしまいました。
大竹しのぶの台詞まわしからは、上流階級出身であるブランチから滲み出てくるはずの品性は感じることはできませんでした。大竹しのぶならではの演技の”クセ”が強くて・・・「後妻業の女」感が抜ききれていないのです。大竹しのぶは、役柄が乗り移ったかのようになりきってしまう”北島マヤ”タイプの女優ではなくて・・・良くも悪くも”大竹しのぶ”は、何を演じても”演技のうまい大竹しのぶ”でしかないような気がします。「欲望という名の電車」さえも、女優”大竹しのぶ”を見せつける題材として、いままでの、どの大竹しのぶの出演作と変わらないのかもしれません。
シアターコクーン・オンレパトリー2017 DISCOVER WORLD THEATRE VOL.3
「欲望という名の電車」
作 : テネシー・ウィリアムズ
演出 : フィリップ・プリーン
出演 : 大竹しのぶ、北村一輝、鈴木杏、藤岡正明
2017年12月8日~12月28日、Bunkamura シアターコクーンにて公演